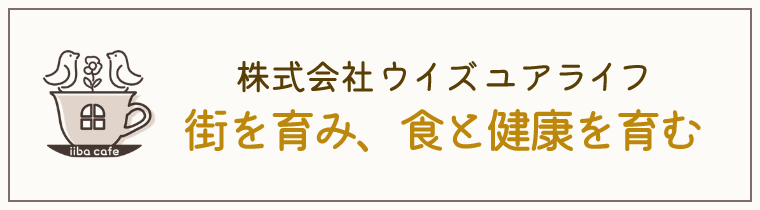水虫の概要
水虫は、田んぼで耕作をしていた人の足に水虫ができたことから、水の中にいる虫に刺されたと考えられたことに
由来するという説があります。
イギリスでは、日本人に比べ一般人には少なく運動選手に多いことからathlete’s foot(運動選手の足)と
言われているそうです。
さて、通称 水虫は、白癬菌(はくせんきん)による感染症で、足に水疱・発赤・痛痒感を伴うのが通称、
水虫と言います。
また水虫には、「角化型白癬(かくかがたはくせん)」と「汗疱状白癬(かんぽうじょうはくせん)」の2種類が
あります。
白癬菌による感染症は、感染する場所によって呼び方が異なります。
皮膚(掌、足、頭、太股の内側、陰部を除く)に感染すると田虫となり、太股の内側や陰部に感染すると
陰金となり、頭に感染すると白雲となります。(白雲は子供に起こりやすい)
白癬菌が高湿度を好むため、いずれも高温多湿の梅雨の頃から秋口にかけて症状が悪化します。
白癬菌が特に足に感染しやすいのは、白癬菌に触れやすいからと、高湿度環境が長時間維持されるからです。
特に、靴を長い時間履きつづけると通気性が悪くなり蒸れて、菌の活動が活発となるからなのです。
日本では梅雨から夏場の高湿度な環境が長く続くため、靴を履いている時間が長い欧米人より感染率が高く、
一般的な病気となっています。
また、糖尿病や免疫力の低い人、治療でステロイド内服をしている人は、水虫になりやすいと
言われています。
水虫の治療
治療法は、抗真菌薬の内服・外用です。
自覚症状がある時点で角質の奥深くまで白癬菌が浸透していることが多く、また白癬菌を完全に殺菌することは
難しいため、自覚症状が無くなっても皮膚が完全に新しいものに入れ替わる1ヶ月程度は治療の継続が
必須です。
かゆみなどの症状が無くなったので、また冬になり乾燥すると白癬菌の活動が弱まるため、治ったと思って
治療を止め再発させてしまう方が多いです。
このため水虫は治しにくく再発しやすい病気と誤解されている面がありますが、しっかりとした対策と治療、
更にその継続さえあれば完治は容易な病気なのです。
水虫は伝染しやすい病気とも言われています。
白癬菌自体の感染力は弱く、白癬菌が長く皮膚に密着した上で多湿環境が維持されないと感染はしません。
しかし、垢として角質ごと落下した白癬菌は数日は生存できるため、これがスリッパ・足拭きマットなどを介して
非感染者の足裏などの皮膚に垢ごと付着し、高湿度などの環境が整っていた結果として伝染することは
容易に懸念されます。
このため家族などで水虫感染者が居る場合は、スリッパや足拭きマット等を専用にするなどの配慮が必要です。
長らく通気の悪い革靴を長時間履いたままになりやすいサラリーマン男性に多かったため、社会的には大人の
男の病気という風に理解されている面がありますが、性別などは全く関係なく、また白癬菌自体は自然界に
多く存在する真菌(カビ)なのです。
至近に対策を行っていない感染者がいれば感染しうる機会は多くなりますが、感染しやすさはあくまで
湿度や足などの環境に大きく影響されます。
実際、女性の間で革のブーツが流行すると、女性の水虫感染者が増えるという相関関係もあるのが水虫です。
水虫の予防
予防は、水虫既感染者との特に足まわりの直接・間接接触を避け、感染しうる機会を減らし、
足を清潔に保ち長時間高湿度にならないようにすればいいのです。
靴下をよく取替え、通気性の良い靴にするなども足の湿度を下げることに効果的です。
最近では五本指靴下があるので、それを履くことも予防に繋がると思います。
足を清潔に保つことは、白癬菌が定住している垢が長時間付着することを防ぐことになるからです。
既感染者が足拭きマットの共用をさけ、足を清潔に保ち垢の落下を防ぐなど、非感染者と接触させないように
するとともに、しっかりとした治療を行うことが、非感染者への感染を防止する事になります。
何度も言いますが、自然に治る事はありません。
根気よく治療する事が家族への思いやりかもしれませんね。